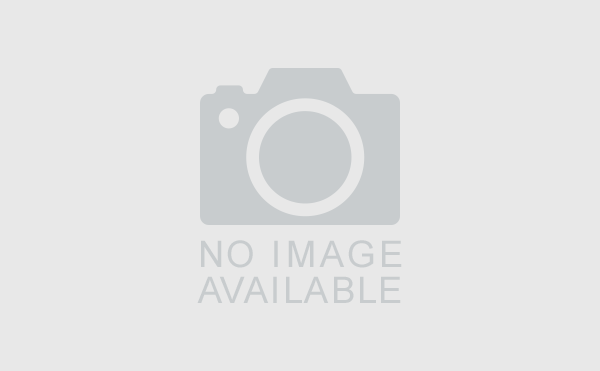元国税審判官による所得税法のColumn(No.9)-「非課税所得」とは?①
「所得税法は難しい」。わが国の所得税法は、包括的所得概念を採用しながらも、①社会政策的な要請、②担税力の有無、➂実費の補填、④少額不追求[1]、⑤二重課税の排除等、様々な観点から、所得であっても課税しない非課税所得を規定しています。今回から、非課税所得に分類されてはいますが、そもそも課税・非課税の線引きが難しいものについて検討していきます。
1.非課税所得の概要
所得税法9条1項には、(1)利子所得関係のもの(同項1・2号)、(2)給与所得関係のもの(同項3~8号)、 (3)譲渡所得関係のもの(同項9・10号)、(4)配当所得関係のもの(同項11号)、(5)その他のもの(同項12~18号)が列挙されています。今回から、「その他」に分類される項目のうち、他の税目との境界線が問題となる、相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(同項16号) を取り上げます。 (なお、次回以降で、同じく課税・非課税の線引き、さらに所得分類が容易でない損害保険金等(同項17号)を取り上げる予定です。)
2.相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの
所得税法9条1項16号は、相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するものを非課税としています。このような資産を譲り受けた側では、相続税や贈与税が課税されるため、被相続人や贈与者が保有していた期間に生じた値上がり益に対し課税することは、それが未実現ということもあり、国民的な理解が得られないということで、限定承認[2]に係る相続及び包括遺贈の場合を除き、相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するものには所得税を課さないこととし、その代わり、相続人ないし受贈者は、被相続人ないし贈与者が保有していた当該資産の所得価額を引き継ぐこととされています。
ところで、相続、遺贈又は個人からの贈与により取得する、いわゆる相続財産の外延が問題となった重要な判例が存在します。それは、マスコミでも大きく取り上げられ、訴訟を支援してきた税理士の活躍も大きく報道された年金二重課税事件(最高裁平成22年7月6日第三小法廷判決)です。以下では、本事案の各裁判所の判断の変遷も含め、詳細に見ていくこととします。
【年金二重課税事件】
<第一審>長崎地裁平成18年11月7日判決・訟月54巻9号2110頁、<控訴審>福岡高裁平成19年10月25日判決・訟月54巻9号2090頁、<上告審>最高裁平成22年7月6日第三小法廷判決・判時2079号20頁
保険契約の概要
X(原告・被控訴人・上告人)の夫Aは、B生命との間で、Aを被保険者、Xを保険金受取人とする年金払特約付生命保険契約(以下「本件保険契約」という)を締結し、保険料を負担していた。本件保険契約には、死亡一時金として支給される4,000万円の他、特約として、10年間にわたり230万円ずつ支給される生活保障年金(以下、当該特約に基づき受給する権利を「本件年金受給権」という。」が付されていた。
事案の概要
Xは、Aの死亡に伴い、平成14年11月、死亡一時金に加え、第1回目の生活保障年金230万円(以下「本件年金の額」という。)から源泉徴収税額22万800円を控除した残額の支払いを受け、相続税の確定申告において、旧相続税法24条1項1号の規定に従い、本件年金受給権の価額を1.380万円と計算し、相続税の課税価格に算入した。他方、Xは、平成14年分の所得税の確定申告では、本年年金の額を収入金額に算入していなかった。これに対し、所轄税務署長は、本件年金の額から、夫Aの既払い保険料に基づく必要経費9万2,000円を控除した220万8,000円をXの平成14年分の雑所得と認定し、更正処分等をしたところ、Xは、本件年金は、相続税法3条1項1号のいわゆるみなし相続財産に該当し、所得税法9条1項15号(平成22年法律6号による改正前のもの。現16号)により所得税を課することができないと主張して、更正処分の一部取り消しを求めた。
争点
本件の争点は、①本件年金が所得税法上の非課税所得に該当するか、より具体的には、相続税の課税対象となっている年金受給権に基づいて受取る各年の年金が所得税の対象となるか否か、仮になるとした場合その全額かあるいはその一部か、という点と、②所得税が非課税とした場合、生命保険会社が行う源泉徴収も違法となるか、という2点である。本件は、第一審の長崎地裁が原告の主張を全面的に認めたものの、控訴審である福岡高裁は、第一審の判断を覆して、一転、課税庁の主張を全面的に求めた。これに対し、上告審である最高裁は、かかる高裁の判決をほぼ全面的に否定し、原告勝訴に至った。
第一審判決要旨
長崎地裁は、「相続税法3条1項によって相続財産とみなされて相続税を課税された財産につき、これと実質的、経済的に見れば同一のものと評価される所得について、(二重課税を避ける見地から)、その所得が法的にはみなし相続財産とは異なる権利ないし利益と評価できるときでも、その所得に所得税を課税することは、旧所得税法9条1項15号によって許されないものと解するのが相当である。」として原告の主張を全面的に認めました。
そして、相続税法による年金受給権の評価については、「将来にわたって受取る各年金の当該取得時における経済的な利益を現価(正確にはその近似値)に引き直したものであるから、これに対して相続税を課税した上、更に個々の年金に所得税を課税することは、実質的・経済的には同一の資産に対して二重に課税するものであることは明らかであって、前記旧所得税法9条1項15号の趣旨により許されないものといわなければならない」と判示しました。すなわち、長崎地裁は、年金受給権については、みなし相続財産として相続税が課税済みであるから、その後相続人が毎年受取る年金については、所得税は非課税であるという判断を下しているように思われます。
他方、生命保険会社が行う源泉徴収については、「(年金の支払いをする者の源泉徴収に関する定めである所得税法207条及び209条の規定は))被保険者ないし年金受取人の死亡という保険事故ないしその事実を支給の要件としない年金の支払いに関する規定と解することができる」として、源泉徴収の規定があることを理由に所得課税が正当であるとした被告・国側の主張を退けました。ただし、この判示によれば、生命保険会社による源泉徴収が誤りだったことを意味することになります。しかし、地裁段階では、原告・被告ともこの点を争点としていなかったため、特にこの問題について問題視されることはありませんでした。
次回より、本件の控訴審及び上告審の判断の変遷を見ていくこととします。
(文責) 公認会計士・税理士 霞 晴久
[1] 少額不追求とは、経済的利益のうち、受益の程度が判然としないもの、たまたま受けるもの、儀礼的なものなど、国税庁通達において、課税除外の取扱いとするための税務執行面の実際上の配慮をいう(前掲・注解所得税[六訂版]539頁)。
[2] 限定承認とは、相続において、相続人が相続によって得た財産を限度として、被相続人の債務(一審専属債務を除くすべての債務)及び遺贈を弁済すべきことを了解して相続の承認をすることをいう(民922)。一方、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する(民990)ので、包括受遺者も限定承認をすることができる。なお、所得税法は、「相続人」には包括受遺者を含むと規定している(所法2②)