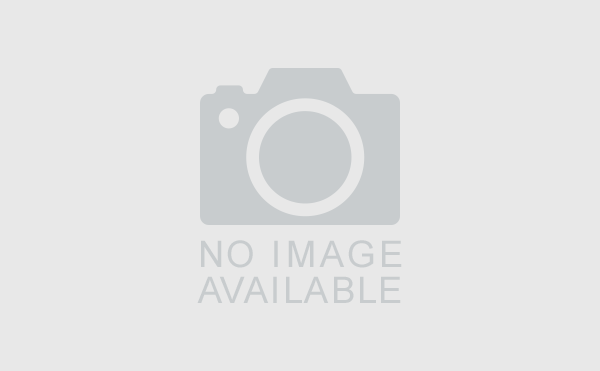元国税審判官による所得税法のColumn(No.8)-「帰属所得」とは?
「所得税法は難しい」。その年において収入すべき金額には、金銭以外のもの又は権利その他経済的な利益を含むとされています。本稿では、観念上消費と捉えられるもののうち所得に含まれるとされる帰属所得について検討します。
本稿第3回で述べたとおり、ヘイグとサイモンズの包括的所得概念の等式(所得=蓄積+消費)から、「消費」は所得の構成要素であることが分かります。ここでいう「消費」とは、一般的には対価を支払って物品(特に消費財等)を購入し、又は役務の提供を受けることをいいますが、例えば、保有資産の使用や自己の労働力の提供など、対価の支払いがない場合であっても、「消費」を観念することは可能です。これをヘイグとサイモンズの包括的所得概念の等式に当てはめると、保有資産の使用や自己の労働力の提供についても所得として把握することができることになるので、特別に、このような所得を「帰属所得(Imputed Income)」と呼んでいます。ただし、帰属所得は、包括的所得概念から導かれるとはいっても、あらゆる消費財の保有や自己の労働から帰属所得が生じるとなると、その範囲が際限なく拡大してしまい、また、それらを金銭的に測定するのも事実上困難であるところから、棚卸資産の自家消費等、次の例外を除いて帰属所得に課税されることはないこととされています。
- 以下の場合、当該資産の消費時の価額について総所得金額に算入する(所法39)
- 棚卸資産を家事のために消費した場合の時価消費
- 山林を伐採して家事のために消費した場合
- 農産物を収穫した場合、当該農産物の価額を総収入金額に算入する(所法41①)
棚卸資産の自家消費に対する課税の問題について、所得税法39条の規定の解釈が問題となった大阪地裁昭和50年4月22日判決(税資81号277頁)は、「たな卸資産を自家消費した場合には、顧客に販売したのではないから、現実に収益が生じているものではないのに、右規定がこれを総収入金額に算入すべきものとしているのは、たな卸資産は通常販売価額で譲渡されるものであって、自家消費の場合にも、経済的には、当該商品を顧客に販売したうえ、右売上金で同一商品を他の販売業者から購入した場合とその効果を一にするからであると解される(右の場合に、販売価額による売上収入があったものとされることは明らかであろう)」と判示しています。すなわち、たな卸資産の自家消費について、通常の取引を想定し、同一製品を他の販売業者から買戻したと擬制するという考え方を示したといえます。
ところで、棚卸資産等の自家消費について総収入金額に算入する場合、実務的には、当該棚卸資産の価額をいくらで評価すべきかの問題が提起されます。これについては、当該棚卸資産が、その消費をした者の販売用の資産であるときは、当該消費の時におけるその者の通常他に販売する価額により、またその他の資産であるときは、当該消費の時における通常売買される価額によるものとされます(所基通39-1)。しかしながら、棚卸資産等の自家消費である以上、外部から当該棚卸資産の対価として経済的利益の流入がある訳ではないので、担税力の面から問題が残ることになります。そこで、特別の場合を除き、自家消費した棚卸資産の取得価額をもって収入金額とする、すなわち、結果的に課税は行われないようにする処理も認められることとされています(所基通39-2)。ただし、総収入金額に算入される金額が、所得税法基本通達39-1にいう通常他の販売する価額(あるいは通常売買される価額)に比して著しく低額でない場合に限られます。ここでいう著しく低額でない場合とは、通常他に販売する価額等の概ね70%以上の場合をいうとされています。この70%というのは、一般の棚卸資産の場合、その差益率がおおむね30%以下であるところから付されたものとされています[1]。
[1] 『平成29年版 所得税法基本通達逐条解説』大蔵財務協会477頁参照。
(文責)税理士・公認会計士 霞 晴久