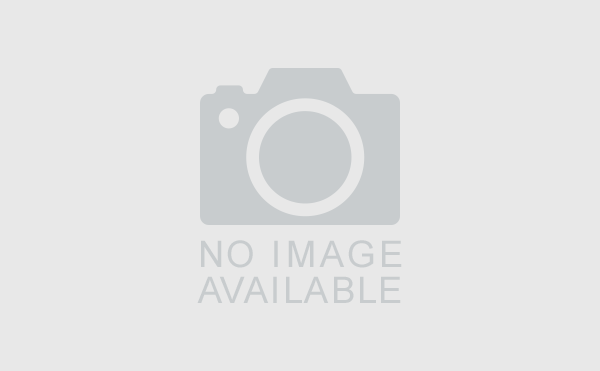海外赴任ガイド別冊『帰国.JP ただいま日本』2021年夏号に「租税条約にいう短期滞在者の免税規定について」というテーマで寄稿しました。
「ただいま日本発行事務局」が、日本通運株式会社の海外ネットワークを通じて、海外在住の方々に無料配布している雑誌「帰国.JPただいま日本」第8版に、海外主張者のみならず、場合によっては海外赴任者にも関係のあるいわゆる183日ルールについて、以下の文章を寄稿いたしました。
1.はじめに
海外出張者が滞在国において課税を受けるか否かを判定するルールとして、いわゆる183日ルールが存在することは有名ですが、ここでいう183日のカウントの仕方には国によって複数の方法があることはあまり知られていません。そこで本稿では主要国におけるいくつかのバリエーションを見た上で、その適用関係について整理してみたいと思います。
2.OECDモデル条約 第15条《短期滞在者の免税》
国際間の二重課税を回避するための規範としてOECD(経済協力開発機構)が加盟各国に採用を勧告しているOECDモデル条約第15条給与所得2項では、国境をまたがる給与について以下のように規定しています。
「2. 一方の締約国の居住者が他方の締約国において行う勤務について取得する報酬に対しては、次のa)からc)までに掲げる要件を満たし場合には、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
a) 当該課税年度において開始し、又は終了するいずれの12箇月の期間においても、報酬の受領者が当該他方の締約国内に滞在する期間が合計183日を超えないこと。
b) 報酬が当該他方の締約国の居住者でない雇用者又はこれに代わる者から支払われるものであること
c) 報酬が雇用者の当該他方の締約国内に有する恒久的施設によって負担されるものでないこと。」
例えば、日本企業に勤務するAさん(日本の居住者)が、米国に出張して同国に一定期間滞在する場合、上記のa)~c)の要件をすべて満たせば、米国では課税されず、日本でのみ課税されることになります。このa)に規定されている183日の期間がいわゆる「183日ルール」の根拠となるものです。ただし、この規定振りは少々分かりにくい表現になっていますので、詳しく説明すると以下のとおりとなります。
<OECDモデル条約における183日のカウント方法>
課税年度というのは、カレンダー・イヤー(暦年)とする国が多い中、例えば上記の例でAさんが2021年中に米国に4月1日から10月31日まで滞在していたとしましょう。課税年度である2021年において、米国における滞在が開始された4月1日から12か月後である2022年3月31日までのAさんの米国滞在期間、及び米国における滞在が終了した10月31日から遡ること12か月である2020年11月1日からの期間におけるAさんの米国滞在期間はいずれも7か月間であり183日を超えるので、上記のa)の要件は満たされず、この期間の給与については米国で課税されることになります。183日のカウント方法が問題となるのは、例えばAさんが2021年の8月1日から年末まで滞在していたケースですが、2021年中の滞在期間が183日に満たなかったとしても、年明け後の滞在期間によって、滞在国での課税が不可避という可能性も生じてくることとなります。
日本が締結する租税条約は、大きく分けて、OECDモデル条約(上記a))と同一又は類似の規定振りか、その年(暦年)で判定するかのいずれかとなっていますが、以下で主要国との租税条約の規定振りについてまとめてみたいと思います(2018年10月1日現在)。
3.日本が締結する主要国との租税条約(給与所得条項)の規定の概要
(1)OECDモデル条約と同一又は類似の規定となっている国
米国、オランダ、英国[1]、シンガポール[2]、ドイツ、フランス、メキシコ[3]
(2)その年を通じて合計183日を超えないと規定している国
イタリア、インドネシア、オーストラリア[4]、カナダ、スペイン、タイ、韓国、中国、ハンガリー、ブラジル、ヴィエトナム、ベルギー、ポーランド、マレイシア、ロシア
(3)当該課税年度及びその「前年度」を通じて合計183日を超えないと規定している国
インド
上記(2)のその年で判定する国々では、例えば歴年をまたぐ滞在の場合、連続では183日を超えるが、各暦年で見れば183日に満たないことになるため、課税されないケースもありうるということになります。
4.短期滞在者の免税規定は日本企業の駐在員にも適用できるか?
ところで、これまでの議論は、主として海外出張者のケースでしたが、この短期滞在者の免税規定が日本企業の海外駐在員にも当てはまるかについて検討したいと思います。
日本企業の海外駐在員の赴任期間の平均は3年から5年程度と考えられますが、そうすると、上記3.(2)の国[5]に赴任するケースで、かつ赴任した年と帰任する年が短期滞在者免税規定の適用がある可能性がありそうです。
しかしながら、短期滞在者免税には、OECDモデル条約が示しているように、b)とc)の要件も満たさなければならず、わが国が締結する実際の租税条約も全く同様の要件を置いているため、以下この要件該当性を検討してみたいと思います。
(1)給与の支払者は派遣元である日本の親会社であること
OECDモデル条約(b))では、「報酬が当該他方の締約国の居住者でない雇用者又はこれに代わる者から支払われるものであること」と規定しています。要は赴任先の日本企業の子会社から給与の支給を受けるような場合は対象外としているのです。日本企業の海外駐在員の給与は、通常、赴任先の子会社から支給を受けるのが通例ですし、モデル条約にいう「勤務について取得する報酬」には、金銭で支給される給与のみならず、住宅の無償貸与やカンパニーカー等の現物給与も含まれると考えられますので、親子会社間の給与の負担の問題は措くとしても、全ての給与の支払を日本の親会社とする、あるいはそのように切り替えるというのは実務上の周到な準備が必要となります。
(2)給与について日本の海外支店に負担させないこと
OECDモデル条約(c))では、「報酬が雇用者の当該他方の締約国内に有する恒久的施設によって負担されるものでないこと」と規定しています。ここでいう恒久的施設とは、日本企業の海外支店を指します[6]。すなわち、上記(1)は海外子会社に赴任するケース、(2)は海外支店に赴任するケースとご理解ください。日本企業の海外支店に赴任する駐在員は、基本的には100%その海外支店のために勤務する訳ですから、その日本人駐在員の給与について海外支店が負担できないとなると、海外支店自体の所得計算上不利となるため、敢えてそこまでする必要があるかどうかという経営上のジャッジメントの問題となります。要は、支店所得の節税と駐在員給与課税の節税のどちらに重きを置くかの判断が要求されるといえるでしょう。
以上から、上記3.(2)の規定を置く国に赴任する日本企業の海外駐在員の赴任年と帰任年について短期滞在者免税の規定を適用することは実務上かなりハードルが高いといえそうです。
5.最後に
本稿における考察はあくまで租税条約上の短期滞在者の免税規定から検討を加えるもので、各国の国内法については全く考慮していません。したがって、海外出張者及び海外駐在員の滞在国における課税関係については、同国の税務の専門家にご相談ください。
[1] 当該課税年度又は賦課年度で判定するとしている。
[2] 「継続するいかなる12箇月の期間においても」という規定振りとなっている。
[3] 同上
[4] 所得年度又は課税年度で判定するとしている。
[5] 上記3.(1)の国々では、赴任の翌年及び帰任の前年の滞在期間もカウントされるので、183日ルールを適用する余地はないと考えられる。
[6] 支店形態以外にも恒久的施設と判定されるケースは複数存在するが、本稿では、話を単純化するため説明を省略する。
(文責) 税理士・公認会計士 霞 晴久