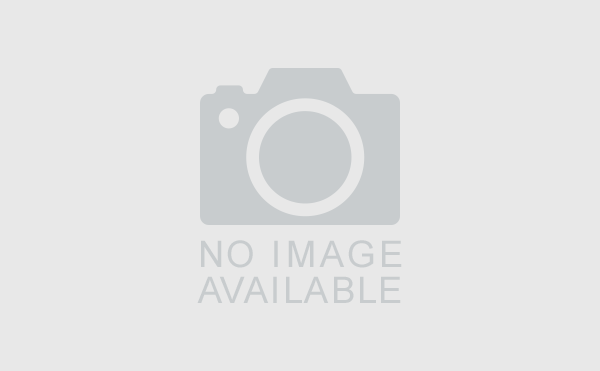元国税審判官による所得税法のColumn(No.2)-「権利確定主義」と「発生主義」
「所得税法は難しい」。シリーズ第2弾は、「会計学」vs「租税法」における最重要概念についてです。企業会計から財務・経理の世界に入った筆者の永遠のテーマでもあります。
所得税は暦年を課税対象期間としていますので、収入がどの年度に帰属するか、すなわち所得の年度帰属は極めて重要な課題です。会計学では、収入の帰属[1]について、伝統的に、現金主義(Cash Base)と発生主義(Accrual Base)を一種の対立概念として捉えてきましたが、税法の世界においても、借用概念として便宜上この2つの考え方を採用しております(所法67など)。所得税法36条1項は、「収入金額とすべき金額」又は「総収入金額に算入するべき金額」は、「収入すべき金額とする」と規定しています(前者は一見何を言ってるか分かりませんが、その述語部分を『所得の金額とする』と読み替えてよいと思われます)ので、「収入すべき金額」とは何を指すかが問題となりますが、条文上の「収入すべき金額」の用語を「収入すべき(法律上の)権利が確定した金額」と文言を補足することで、いわゆる「権利確定主義」を導き出し、かかる「権利確定主義」を広義の発生主義に含まれる[2]ものと整理し、会計学のいう発生主義との整合性が図られています。
多くの裁判例[3]では、収入金額について「収入すべき金額」としているのは、「現実の収入がなくても、その収入となる権利が確定した場合には、その時点で所得の実現があったものとして右権利確定の時期の属する年分の課税所得を計算するという建前(いわゆる権利確定主義)を採用しているものと解される。」とし、「課税にあたって常に現金収入の時まで課税することができないとしたのでは、納税者の恣意を許し、課税の公平を期しがたいので、徴税政策上の技術的見地から、収入の原因となる権利の確定した時期を捉えて課税することとした」と判示しています。
権利確定主義の意義について、利息制限法制限超過利息事件の控訴審(福岡高裁昭和42年11月30日判決・民集25巻8号1153頁)は、「権利確定主義は会計理論上の発生主義に対応すると考えられるものであるが、右会計理論が企業の経済活動を把握するための会計技術的側面から生じたものであるのに対し、税法上の権利確定主義は右理論に対応しながら、税法上いかなる時点で収入金額の発生を確実なものとして認識しうるかを、主として法律的側面からとらえようとしたものと解すべきであり、収入の権利確定の時期としては、原則として法律上権利の行使ができるようになった時を基準と解するのが相当である」と判示しています。
しかしながら、発生主義は極めて抽象的な概念であるため、企業会計上実際に収益を認識するためには、「実現」という概念を用います[4]。そうすると、次に「実現主義」と「権利確定主義」の関係が問題となります。この点については次回以降で論じたいと思います。
[1] 会計学の文脈では、通常、『収益の認識』という用語を用いるはずですが、租税法上の議論として平仄を合わせるため、ここでは『収入の帰属』という用語を用います。
[2] 金子宏『租税法(第21版)』285頁「(所得税法36条1項の)規定は広義の発生主義のうちいわゆる権利確定主義を採用したものである、と一般に解されている。」
[3] 最高裁昭和40年9月8日第二小法廷判決・刑集19巻6号630頁、同昭和40年9月24日第二小法廷判決・民集19巻6号1688頁、同昭和49年3月8日第二小法廷判決・民集28巻2号186頁、同昭和53年53年2月24日第二小法廷判決・民集32巻1号43頁など。
[4] 企業会計原則では、「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る」(同原則第2の1のA・3のB)と定めており、又「実現主義」については、「期間収益を認識(記録)する際に『実現』を要件とすることをいう」と定義(会計大辞典)しているように、実現主義は所得の年度帰属を決定する考え方として理解されています。
(文責) 税理士・公認会計士 霞 晴久