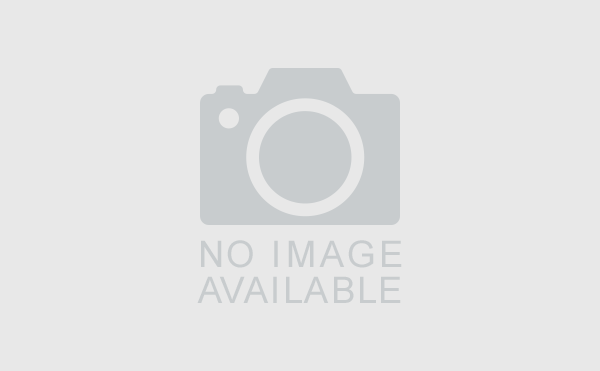元国税審判官による所得税法のColumn(No.1)-「事業」と「業務」
「所得税法は難しい」。筆者は常日頃から所得税法を支える諸概念の奥深さについてそのように感じています。本シリーズでは、所得税法の背後にある基礎的概念・判断枠組み等について紹介いたします。
「事業」という用語と「業務」という用語は、どちらも日常的に用いられ、両者を別の物として意識的に区分することはありません。ところが、所得税法では、これらが用いられる局面によっては両者の違いが重要な意味を持つようになってくるので注意が必要です。
特に重要なのが、不動産所得を生ずべき不動産等の貸付けが「事業」といえるものか、「業務」といえるものかの区分です。所得税法では両者は規模の違いであるとし、「事業的規模」の貸付けであるのか、「業務的規模」の貸付けであるかについては、いわゆる「5棟10室基準(所基通26-9)」を用いて判断することになっています。不動産所得を生ずべき事業と不動産所得を生ずべき業務の具体的な相違は、収入から控除する項目の差となって表れます(典型例は青色申告特別控除でしょうか。「事業」であれば最大65万円控除できるものが、「業務」であれば10万円に減額されます)。不動産所得においては、その規模を判断する基準として、「事業」という用語と「業務」という用語が用いられているのであって、所得区分を判断する基準ではないということになります。
一方、所得税法51条《資産損失の必要経費算入》では、資産損失が生ずる局面として、①不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される資産(同1項)、及び②不動産所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供される資産(同4項)というように分類されており、それぞれの必要経費の取扱いが異なるように規定されています。不動産所得については上記の規模的区分が当て嵌まるとして、それ以外は、例えばある資産を使って経済活動を行う場合、当該資産が「事業」の用に供されたのか、「業務」の用に供されたかでその所得区分が異なる(前者が事業所得又は山林所得、後者が雑所得)というように規定されています。山林所得は措くとして、事業所得か雑所得かは必ずしも規模の違いではなく、雑所得はそもそも他のどの所得区分にも分類されない所得であり(所法35)、事業所得該当性は規模以外の要素(*)で判断されるので、かかる規模以外の要素により判断される「事業」と「業務」の違いが所得区分の判定に影響していることになります。
このように、所得税法では、「事業」と「業務」の概念は明確に使い分けられており、それらの相違が所得計算に大きな影響を及ぼしています。しかしながら、上述したようにそれらの相違が必ずしも一貫して用いられていない点に留意しなければなりません。この点も、所得税法が「難しい」と感じる要因の一つと思います。
(*)事業所得とは何かについては数多くの裁判例ありますが、多くの裁判例では、「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生じる所得をいう」(最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決・民集35巻3号672頁)という定義を引用しています。
(文責)税理士・公認会計士 霞 晴久