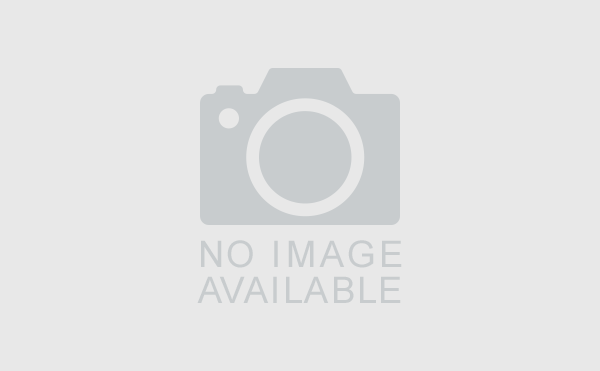元国税審判官による所得税法のColumn(No.6)-「権利確定主義」と「管理支配基準」〈その2〉
「所得税法は難しい」。前回に引き続き、「権利確定主義」と「管理支配基準」関係について検討し、その位置付けについて、筆者なりに整理してみたいと思います。
本稿第5回で取り上げた賃料増額請求事件の最高裁判決では、収入の帰属年分について、所得税法が、いわゆる現金主義でなく権利確定主義を採用したのは、「現金収入の時まで課税することができないとしたのでは、納税者の恣意を許し、課税の公平を期しがたい」からと述べています。ここでいう「納税者の恣意を許し」という理由付けは、法人の収益の帰属年度に係る有名な大竹貿易事件(最高裁平成5年11月25日第一小法廷判決)の判旨[1]でも述べられておりますが、筆者は係る説明の仕方にはやや懐疑的です。何故なら、大竹貿易事件について、裁判所のいう「納税者の恣意」というのは、納税者が意図的に売上債権の計上や回収を遅らせるということを意味することと解されますが、いくら納税をしたくないからといって、いつまでも売上債権を計上しない、回収しないというような納税者は存在しないからです。その点は措くとしても、権利の確定という法的基準のみでは、権利未確定である賃料増額請求事件(係争中の賃料増額請求権により仮執行宣言付き判決に基づき金員を収受した事例)のような場合には対応できないのは明白で、ここで、「法的基準」を補完する経済的な視点としての管理支配基準が求められるといえそうです。
本稿第4回で述べたように、実現主義とは、実現した所得すなわち外部から流入した経済的価値のみを所得課税の対象とする考え方です。賃料増額請求事件における「所得の実現があったとみることができる状態が生じたとき」という判示や、本稿第5回で見た利息制限法制限超過利息事件における「収入実現の可能性が高度であると認められる」ないし「収入実現の蓋然性がある」等の表現振りを見る限り、最高裁は、所得税法39条の、「収入すべき金額」を解釈するに当たり、所得の実現が成立しているか否かを規範[2]として、判断していると解されます。判決では「現実収入」について、別途「自己の所有として自由に処分できる」状態と表現しており、管理支配基準の充足について、かかる段階に到達していることとしていると思われます。
多くの裁判例が引用する権利確定主義の定義でも、「現実の収入がなくても、その収入となる権利が確定した場合には、その時点で所得の実現があったものとして右権利確定の時期の属する年分の課税所得を計算するという建前(下線筆者)」としており、「権利の確定」と「所得の実現」が並列的かつ同等な概念として示されており、裁判所は、所得の実現を判定する過程で、法定な側面である権利確定主義と、それを補完する経済的な側面である管理支配主義を1対のペアとして、後者を前者が包含するものと位置づけている[3]と考えられるのではないでしょうか。
なお、管理支配基準は、「すでに金員を収受」している点から、結果として現金主義と類似し、その境界が不明確となりがちですが、上述したように、管理支配基準は、権利確定主義に包含されるものと位置づけられ、広義の発生主義を構成するものといえ、その意味で現金主義とは異なるものと考えます。
[1] 正確には「収益計上時期を人為的に操作する余地を生じさせる点において、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に適合するものとはいえない」というものである。しかし、仮装・隠ぺい行為は別として、反復・継続する事業活動の中で、納税者が、納税を回避するためだけに、わざわざ売上債権の計上や回収を遅らせることは、一般の資金繰りの観点からは考え難く、実務的には所謂「期ズレ」として処理される類の問題であろう。
[2] 谷口勢津夫『税法基本講義 第4版』(2014年・弘文堂)333頁は、「極めてシンプルな要件について、2つの異なる規範を定立してるとは考えられないので、実現主義こそが所得の年度帰属判定規範として定立されていると解されるのである」と述べている。
[3] 谷口・前掲注2 334頁は、「権利確定主義と管理支配基準とは、相互排他的ないし二者択一的な関係にあるのではなく、むしろ事案によっては、所得の実現の推認の過程で、相互補完的に作用し得る場合もあると考えることがきできよう」と述べている。
(文責) 税理士・公認会計士 霞 晴久