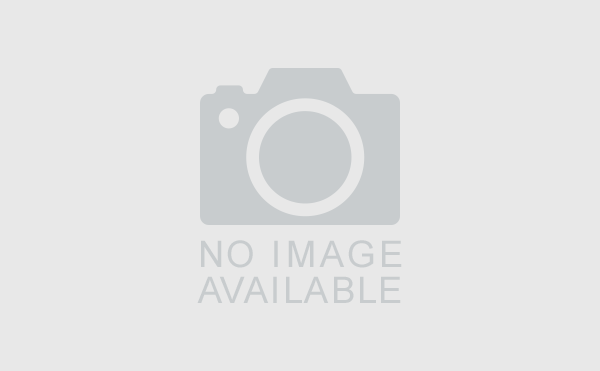元国税審判官による所得税法のColumn(No.10)-「非課税所得」とは?②
「所得税法は難しい」。本稿では、前回から、非課税所得について検討しています。その中で、課税・非課税の線引きが難しいもの、また、他税目との境界線の把握が困難なものとして、年金払いの生命保険金の取扱いについて争われた年金二重払い事件の裁判例について見ていきます。前回、同事件の第一審判決の判旨を取り上げましたので、今回はその控訴審及び上告審についてです。
事案の概要
被相続人の死亡に伴い、死亡一時金に加え、第1回目の年金の支払を受けたXは、相続税の確定申告をした(所得税の確定申告では年金は申告せず)ところ、所轄税務署長から、年金については所得税法上雑所得に当たるとして更正処分を受けたことから、その取消しを求めて出訴しました。第一審の長崎地裁は、年金に所得税を課税することは、旧所得税法9条1項15号によって許されないとして原告の主張を全面的に認めました。国側はこの判決を不服として控訴しました。
控訴審:福岡高裁平成19年10月25日・訟月54巻9号2090頁
控訴審である福岡高裁は、「Xは、〔中略〕、一時金を受け取るのではなく、年金により支払を受けることを選択し、特約年金の最初の支払として本件年金を受け取ったものである。本件年金は、10年間、保険事故発生日の応当日に本件年金受給権に基づいて発生する支分権に基づいて、Xが受取った最初の現金というべきものである。そうすると、本件年金は、本件年金受給権とは法的に異なるものであり、Aの死亡後に支分権に基づいて発生したものであるから、相続税法3条1項1号に規定する『保険金』に該当せず、旧所得税法9条1項15号所定の非課税所得に該当しないと解される。したがって、本件年金に係る所得は所得税の対象となるものというべきである。」と判示し、年金受給の基本権である本件年金受給権と、そこから派生する支分権という権利を提示した上で、両者の法的差異に着目し、一転、控訴人である国側の主張を全面的に認めました。
控訴審判決は、従前の課税実務に従った判断といえますが、判決文を読む限り、「支分権」として示される権利の範囲は、毎年支給される年金の10年分の総額と思われます。これは元々本件年金受給権に基づいてそこから派生するものと解されるため、両者は経済的には同一といえます。したがって、控訴審判決に従うと、地裁判決がいうように経済的二重課税に陥ってしまうことになります。すなわち、控訴審判決がいうように法的性質が異なるからといって、経済的・実質的に同一のものが二重課税となってしまうという問題は残されたままとなります。
なお、支払われた年金に係る所得税の源泉徴収の問題について、控訴審判決は、「居住者に対し所定の生命保険契約に基づく死亡保険金として年金の支払いをする者が、その支払いをする際、その年金について所得税を源泉徴収しなければならないことは明らかである。したがって、(所得税法207条等の)各規定は、所得税法が、所定の生命保険契約に基づいて、死亡保険金として年金の支払いを受ける者に所得が生じることを当然の前提としているものと解される」とし、源泉徴収の規定があることを根拠に、年金についての所得課税があり得ることを正当化しました。
かかる控訴審判決を不服としてXは上告しました。
上告審:最高裁平成22年7月6日第三小法廷判決・判時2079号20頁
最高裁は、上記高裁判決を全面的に破棄し、以下の様に自判しました。(以下引用)
(1)旧所得税法9条1項15号の意義について
同号にいう「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの」とは、相続等により取得したまたは取得したものとみなされる財産そのものを指すのではなく、当該財産の取得によりその者に帰属する所得を指すものと解される。そして、当該財産の取得によりその者に帰属する所得とは、当該財産の取得の時における価額に相当する経済的価値にほかならず、これは相続税又は贈与税の課税対象となるものであるから、同号の趣旨は、相続税又は贈与税の課税対象となる経済的価値に対しては課税所得を課さないこととして、同一の経済的価値に対する相続税又は贈与税と所得税の二重課税を排除したものと解される。
(2)本件年金受給権について
年金の方法により支払を受ける保険金(年金受給権)のうち有期定期金債権に当たるものについては、相続税法3条1項1号の規定により、その残存期間に応じ、その残存期間に受けるべき年金の総額に同号所定の割合を乗じて計算した金額が当該年金受給権の価額として相続税の課税対象となるが、この価額は、当該年金受給権の取得の時における時価(同法22条)、すなわち、将来にわたって受取るべき年金の金額を被相続人死亡時の現在価値に引き直した金額の合計額に相当し、その価額と上記残存期間に受けるべき年金の総額は、当該各年金の上記現在価値をそれぞれ元本とした場合の運用益の合計額に相当するものとして規定されているものと解される。したがって、これらの年金の各支給額のうち上記現在価値に相当する部分は、相続税の課税対象になる経済的価値と同一のものということができ、(旧)所得税法9条1項15号により所得税の課税対象とならないものというべきである。 本件年金受給権は年金の方法により支払いを受ける上記保険金のうちの有期定期金債権に当たり、また、本件年金は、被相続人の死亡日を支給日とする第1回目の年金であるから、その支給額と相続人死亡時の現在価値とが一致するものと解される。そうすると、本件年金の額は、全て所得税の課税対象とならないから、これに対して所得税を課することは許されないものというべきである。
(3)源泉徴収の正当性について
所得税法207条所定の生命保険契約等の基づく年金の支払いをする者は、当該年金が同法の定める所得として所得税の課税対象となるか否かにかかわらず、その支払いの際、その年金について同法208条所定の金額を徴収し、これを所得税として国に納付する義務を負うものと解するのが相当である。 したがって、B社(筆者注:生命保険会社)が本件年金についてした同条所定の金額の徴収は適法であるから、上告人が所得税の申告等の手続において上記徴収金額を算出所得税額から控除し又はその全部若しくは一部の還付を受けることは許されるものである。
検討―本件最高裁判決の意義について
本最高裁判決の意義は、実態面と手続面の2つにあるといわれています[1]。実態面の意義とは、年金受給権としてみなし相続財産とされ、相続税の課税対象となる部分については、旧所得税法9条1項15号に該当し、所得税が非課税となり、従前の課税実務を不適法とした点です。もう一つの手続面での意義は、地裁の判断に従うと源泉徴収が不適法となってしまうところ、次回以降で検討するように、年金払いの死亡保険金について、最高裁判決が整理し決着した方法によって、所得税法208条所定の源泉徴収は適法とされた点です。
(文責) 公認会計士・税理士 霞 晴久
[1] 神山弘行『租税判例百選 第6版』有斐閣2016年65頁参照。