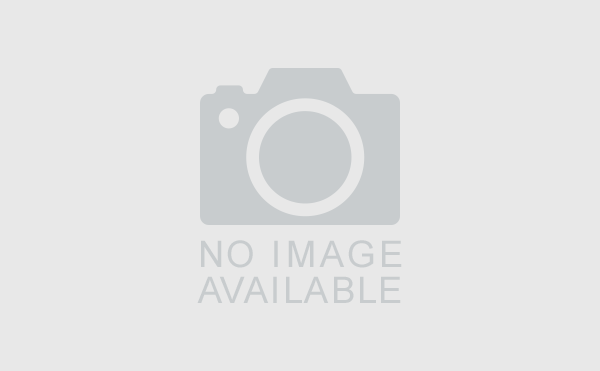元国税審判官による所得税法のColumn(No.4)-「権利確定主義」と「実現主義」
「所得税法は難しい」。シリーズ第2回で述べた発生主義は極めて抽象的な概念なため、会計学でも租税法でも「実現主義」という概念が使われます。今回は特に、「権利確定主義」と「実現主義」の対比から、両者の親和性について検討します。
前回述べたように、現在主要国で採用されている包括的所得概念では、一定期間の全ての利得が所得とされ、その考え方の下では、「収入すべき金額」とは、外部から流入した経済的価値全てが課税所得の対象ということになります。ここでいう、経済的価値の外部からの流入とは、企業会計でいう「実現」の概念と同義に解してよいと思われます[1]。植松守雄氏は、「『権利確定主義』の考え方は、会計学上の『現金主義』に対比する意味での『発生主義』の概念に属し、さらに、収益発生の認識基準としての『実現主義』に概念に対応するものとして一般に理解されている」[2]と述べておられます。
企業会計原則では、「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る」(同原則第2の1のA・3のB)と定めており、又「実現主義」については、「期間収益を認識(記録)する際に『実現』を要件とすることをいう」[3]と定義されているように、実現主義は所得の年度帰属を決定する考え方として理解されております。所得税法においても、最も典型的な商取引の例として、商品販売業者が行う棚卸資産の販売について、当該販売業者の事業所得の総収入金額の収入すべき時期は、当該棚卸資産の引渡しがあった日と定められて(引渡基準。所基通36-8(1))おり、これは、「引渡が権利の確定ないし所有権の移転の最も明白で争いの少ない証拠であり、また税務行政にとって契約の効力発生または所有権移転の事実を最もよく把握し得る時点であるから、その時点をもって権利の確定ないし所有権の移転の時期と見なすのが執行上は最も安全で確実であるという理由によるもの」[4]と説明されています。
企業会計では、例えば収益の実現に到達していない状態を「未実現」と表現します。包括的所得概念を採用する所得税法においては、人の担税力を増加させる利得であっても、未実現の利得及び帰属所得(前回参照)は課税の対象から除外されます。金子宏教授は、「これは、それらが本質的に所得でないからではなく、それらを補足し評価することが困難であるからであって、それらを課税の対象とするかどうかは立法政策上の問題である」[5]と述べられています。所得税法上課税の対象となる未実現の利得には、棚卸資産などの贈与または低廉譲渡が含まれます(所法40)が、これは、特に、「時価」と「取引価格」の乖離における、いわゆる「みなし譲渡」の問題として、租税法の大きなテーマの一つとなっています。しかしながら、会計学では、取引の当事者で合意した価格を時価に引き直すというような作業は要求されないし、また、このような状態を「未実現」という用語で表現することもない点、両者には明確な違いが存在しています。
[1] 谷口勢津夫『税法基本講義 第6版」204頁では、「実現主義は、本来は、実現した所得すなわち外部から流入した経済的価値のみを所得課税の対象とし、未実現の所得は所得課税の対象から除外しなければならないという考え方である」とされています。
[2] 注解所得税法研究会編『注解所得税法〔六訂版〕』(平成31年 大蔵財務協会)216頁。
[3] 会計大辞典
[4] 金子宏「所得の年度帰属」同『所得概念の研究』284頁(1995年 有斐閣)
[5] 金子宏『租税法 第21版』(2016年 弘文堂)185頁。
(文責)税理士・公認会計士 霞 晴久