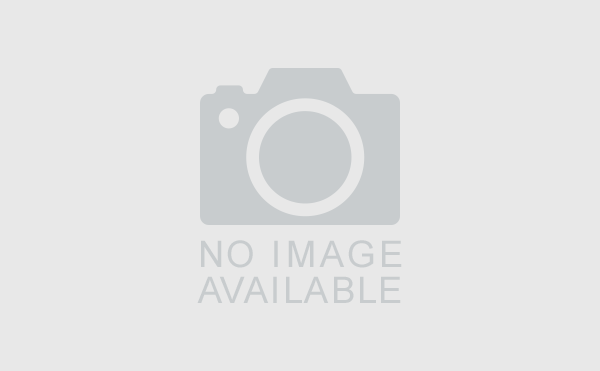元国税審判官による所得税法のColumn(No.3)-「所得」とは何か?
「所得税法は難しい」。前回は、権利確定主義と発生主義について述べましたが、今回は、権利確定主義と実現主義の比較検討に入る前に、そもそも「所得」とは何かについて、歴史的な議論を踏まえ考察いたします。
いわゆる所得の概念には2つの類型があるといわれています。一つが消費型(支出型)所得概念であり、もう一つは取得型(発生型)所得概念です。前者は、所得を消費によって得られる価値に限定して観念し、蓄積に向けられた価値を所得から除外する考え方です。しかし、蓄積に充てられる部分を所得から除外することは富の格差を助長することにつながり、そのことへの不公平感を拭えないことや、そもそも消費の把握・帰属の判定が困難であること等の理由から、実際の制度として採用している国は存在しません。一方、後者は、所得の取得ないし発生に着目して考案された所得概念であり、多くの国の租税制度として実際に採用されています。取得型(発生型)所得概念には、さらに、制限的所得概念と包括的所得概念という学説上の対立があります。
制限的所得概念とは、所得源泉説とも呼ばれ、各種勤労、事業、資産の貸付けなど反復的・継続的に生ずる所得のみを所得として観念し、一時的・偶発的な所得を除外する考え方です。これは、世界で初めて所得税を導入したイギリスや欧州諸国で伝統的に採用されてきた考え方で、これらの国では、資産のキャピタル・ゲイン[1]は、一時的・偶発的なものとして、長い間所得から除外されてきました。
制限的所得概念に対し、人の担税力(租税を負担する能力のこと)を増加させる利得は、すべてその源泉を問わず所得となるとする考え方(包括的所得概念)が、第1次大戦後のアメリカで提唱されました。この概念は、財政学者のヘイグ(Haig)とサイモンズ(Simons)など多くの学者の支持を得て、世界的に普及することとなりました。ヘイグとサイモンズは、包括的所得概念を、「所得=蓄積+消費」の等式で捉えられるとしたのです。ある個人が、一定期間(所得税の世界では、通常、暦年である1年間)に新たに獲得した経済的な価値は、結果的に見て、当該年度内で消費されてしまうか、消費されずに暦年の最終日に純資産として手許に残るかのいずれかとなります。ヘイグとサイモンズの等式はこのことを表しています。なお、暦年の最終日に個人の懐に蓄積されているものは、あくまで当該個人の総資産と総負債を相殺した残りの純額としての資産(純資産)です。ゆえに、この包括的所得概念の考え方は、一定期間に生じた純資産の増加がすべて所得に含まれるという意味で、純資産増加説とも呼ばれています。
わが国では、第2次世界大戦までは制限的所得概念を採用していましたが、昭和24年のシャウプ勧告に基づき、包括的所得概念の採用に大きく舵を切り現在に至っています。現行の所得税法の各規定の中で、包括的所得概念について直接触れている箇所は存在しませんが、次のように、現行制度上この考え方が随所に現れています。
- 所得分類のうち、譲渡所得や一時所得といった一時的・偶発的所得も、課税所得の一部を構成している。
- 10種理の所得分類(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、配当所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得をいう。)のうち、利子所得から一時所得までの9種類のうちのどれにも当たらないバスケットカテゴリーとして、「雑所得」が設けられている(所税35条①)。
- 一部の未実現所得や帰属所得[2]も課税所得に含められる。
- 金銭以外の物又は権利その他の経済的な利益の額も所得を構成する(所法36①)。
- 違法な所得も課税所得に含められる(所基通36-1)。
包括的所得概念が世界で広く支持されるようになった理由として、谷口勢津夫教授は、「租税理論的には、それが最も重要な租税原則の一つである公平負担の原則の要請(担税力に応じた課税の原則)に適合するからである。その指示の背景には、20世紀に入ってからの社会国家(福祉国家)化やそこでの財政需要の増大(戦時には特別な財政事情も加わった)、更には政策手段としての租税の重要性の高まりがあったことも、見落としてはならない。」[3]と述べています。上記5のように、包括的所得概念の下では、その所得の源泉に関係なく課税対象とされるため、違法な所得についても課税の対象となる点に留意する必要があります(違法な所得の論点については、別途論じることとします)。
[1] 例えば、不動産の長期譲渡益について分離課税の対象とするのも、この考え方の名残りといえそうです。
[2] ヘイグとサイモンズの包括的所得概念の等式から、「消費」は所得の構成要素となりますが、ここでいう「消費」とは、一般的には対価を支払って物品(特に消費財等)を購入し、又は役務の提供を受けることをいいます。ただし、例えば、保有資産の使用や自己の労働力の提案など、対価の支払いがない場合であっても、「消費」を観念することは可能です。これをヘイグとサイモンズの包括的所得概念の等式に当てはめると、保有資産の使用や自己の労働力の提供についても所得として把握することができますが、これを「帰属所得(Imputed Income)」と呼びます。
[3] 谷口勢津夫『税法基本講義 第6版』弘文堂2018年197頁
(文責)税理士・公認会計士 霞 晴久